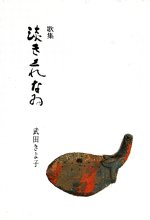2月28日(土)
昨日は地平線会議。291回目。金井シゲさんの登場だった。金井さんのハワイ。前半はいつもの名調子。後半はE本さんハワイ初体験。デジカメ初体験のお話。さらに後半は石川くん登場。熱気球で太平洋横断に飛び立ったが途中で着水。幸運に恵まれ無事にコンテナ船に救出された顛末についての報告。A東君の植村直己賞受賞の話。さらにT村さんの7大陸最高峰をめざす決意。などなど盛りだくさんの話題、それぞれじっくり聞きたい内容のつまみ食いだった。
午前中は墨田区にある「すみだ環境ふれあい館」に関野吉晴探検資料室が開設され区長から感謝状をうける関野さんる事になり、その開設式があった。地平線の仲間とともに出席。墨田区は関野さんの出身地。資料室は廃校になった小学校を転用した環境の教育施設。もともと墨田区は雨水利用では先進区だ。その館に大きな目玉ができた。小学校の転用施設だから、展示資料の保護にはよい環境ではないかも知れない。しかし手作りを大事にする関野さんらしい場所を得た感じだ。子どもたちにていねいにカヤックやソリの説明をする姿は、人間好きが伝わってくる。
展示された140点のすばらしい写真のかなりの部分は、人間の笑顔だ。人と人のていねいなつきあいが現れた写真だ。
子どもたちにぜひ見せたい資料館だ。墨田区近くに住んでおられる方、ぜひ見学してください。
入館料無料。場所は
墨田区文花1-32-9 旧文花小学校 東武鉄道亀戸線「小村井駅」下車10分