3か月ぶりの病院、心電図をとってからの診察なので、いつものように一日がかりだと思っていた。しかし新型コロナのせいなのか病院はガラガラで10時には全部終わってしまった。半年前と変化なしということでとりあえずオーケー。朝の天気予報で晴は本日迄と言っていたので、そのまま高尾山に行くことにした。高尾駅から小仏峠城山と空いているコースを考えていた。
- 陣馬高原下・三密禁止とか
- 陣馬山頂の白馬、空が青い
11時40分、ちょうど陣馬高原下行のバスが出るところだったので急いで飛び乗った。12時15分に陣馬高原下から歩き始めた。陣馬山までは昔望遠鏡を担いで上がった。我が高校の天文部は別名天文山岳部だった。1時半陣馬山の白馬にでた。周囲の茶屋はほとんど休業、人は少ないのでちょっと寂しいが空は真っ青に晴れて美しい。コロナのおかげでヒコーキが飛ばず、車も少なくなったので空気はきれいになった。ここから高尾山までは、山岳耐久レールの練習で毎週来ていた。還暦のころは2時間で行くことができたが今は3時間はかかるだろう。しかしまだ1時半、遅くとも4時半には高尾山口駅に着くはずだ。
- 明王峠の茶屋、休業中
- 誰も採らない、食べ過ぎた
明王峠まで25分。先日FBで城定くんがこの辺りまで道路整備に来ているという記事を見た。コロナのせいで人が入らず土砂崩れ、倒木が相次いでいるのを見かねてボランティアで黙々と整備している。行政ができないなら自分でやるよ!この精神が山中先生のいうファクターXだろう。コロナが日本で爆発的に広がらなかったことはそれぞれ自分たちでできちことは率先してやっていく習慣が社会にあることだと私は思っている。城定君の行動、おせっかいだがこういう人がいるから非常時でも動いて行くのだろう。
- 小仏峠、茶屋は崩れている。
- 城山茶屋、ここも休業中
皆さんのお世話で快適に歩きながら小仏峠まで1時間半で到着、スマホの充電をしてこなかったのでヤマップの記録をここでストップ。城山下のまき道は土砂崩れで通れないので山頂の茶屋に行くが、ここも休業中。
城山からは一丁平をとおり琵琶滝経由で降りてきた。高尾山頂から薬王院などを通ると人が多いだろうと思っていたが、ケーブル駅に着くとほとんど人はいない。高尾山観光は外国人観光客で持っていたのだということを実感。このままでいけば私の「好みの山」リストに復帰するなあ













 6月に入っても自主自粛を続けると言った舌の根も乾かないうちに、立川の下島さんから御岳山に行くよ!との誘いがあった。紅葉屋さんが再開するから山上でおそばを食べようとのこと。3月12日に紅葉屋創業90周年を祝うはずだったが、コロナで延期になっている。いつできるかの相談もかねてのことだ。
6月に入っても自主自粛を続けると言った舌の根も乾かないうちに、立川の下島さんから御岳山に行くよ!との誘いがあった。紅葉屋さんが再開するから山上でおそばを食べようとのこと。3月12日に紅葉屋創業90周年を祝うはずだったが、コロナで延期になっている。いつできるかの相談もかねてのことだ。 そうだと言ってもいつ終息するかもわからない。集まったところで相談の内容はない。目的はおいしいおそば。その前に久しぶりの登山を楽しむことにした。平日の昼間なので電車はすいている。しかし御岳駅からバスが混むかのもしれないので、川井駅から歩いて行くことにした。山頂までほぼ9キロ、杉並木の急登がある。ゆっくりのんびり歩いて行くことにした。
そうだと言ってもいつ終息するかもわからない。集まったところで相談の内容はない。目的はおいしいおそば。その前に久しぶりの登山を楽しむことにした。平日の昼間なので電車はすいている。しかし御岳駅からバスが混むかのもしれないので、川井駅から歩いて行くことにした。山頂までほぼ9キロ、杉並木の急登がある。ゆっくりのんびり歩いて行くことにした。 その様子は動画を作成中なのでそちらを近々アップします。途中でケーブルカーを見ると誰も乗っていない。帰りは雨も降っていたので義理でのって下った。久しぶりのケーブルカー、なかなか楽しかった。バスに乗ろうと思ったが30分後だったので歩いた。バスがつくのと同時に御嶽駅に着いた。久しぶりの遠出、ちょっと後ろめたかったが山の空気はよく、中央線は一人置きに座っているので、三密になっている場所はまったくなかった。
その様子は動画を作成中なのでそちらを近々アップします。途中でケーブルカーを見ると誰も乗っていない。帰りは雨も降っていたので義理でのって下った。久しぶりのケーブルカー、なかなか楽しかった。バスに乗ろうと思ったが30分後だったので歩いた。バスがつくのと同時に御嶽駅に着いた。久しぶりの遠出、ちょっと後ろめたかったが山の空気はよく、中央線は一人置きに座っているので、三密になっている場所はまったくなかった。 5月26日に新型コロナの自粛が解除になった。東京は6月1日に解除の予定だったが、政府が速く解除するようにいろいろ操作をしたようだ。5月23日には感染者はたった2名になり、自粛解除の流れは一気に加速した。東京の町中は関西地区が解除になったころから一緒に解除になった気分らしい。
5月26日に新型コロナの自粛が解除になった。東京は6月1日に解除の予定だったが、政府が速く解除するようにいろいろ操作をしたようだ。5月23日には感染者はたった2名になり、自粛解除の流れは一気に加速した。東京の町中は関西地区が解除になったころから一緒に解除になった気分らしい。 ジジババにとってはまだしばらくは外出、外食などできないだろう。皆はしゃいでいる。我が家のすぐそばまでパチンコ屋の入場券の配布の人たちが並んでいる。前よりももっと危険な状況になっているのであと1か月ぐらいは自主自粛の予定だ。膝が痛くなったので家中登山は出来なくなったが、朝早く散歩は続けている。
ジジババにとってはまだしばらくは外出、外食などできないだろう。皆はしゃいでいる。我が家のすぐそばまでパチンコ屋の入場券の配布の人たちが並んでいる。前よりももっと危険な状況になっているのであと1か月ぐらいは自主自粛の予定だ。膝が痛くなったので家中登山は出来なくなったが、朝早く散歩は続けている。

























 我が家の近所にも玄関に蘇民将来の「符」が飾ってある家もある。この家は「蘇民将来」の子孫ですよという証明書みたいなものである。
我が家の近所にも玄関に蘇民将来の「符」が飾ってある家もある。この家は「蘇民将来」の子孫ですよという証明書みたいなものである。



 狛カエルは埼玉県のみずほ台駅から3キロほどのところにある水子貝塚のすぐ脇にある神社(名前を忘れた)にある。最近交通安全のために、無事カエルをもじったもののようだ。あまりおもしろくない。水子貝塚博物館の方が興味深かった。
狛カエルは埼玉県のみずほ台駅から3キロほどのところにある水子貝塚のすぐ脇にある神社(名前を忘れた)にある。最近交通安全のために、無事カエルをもじったもののようだ。あまりおもしろくない。水子貝塚博物館の方が興味深かった。 狛ゾウ 仏教の発祥はインドだからお寺に狛ゾウがあってもいいだろう。四国お遍路に行った時に第62番だったかにも門前い狛ゾウがいた。これは文京区の白山の交差点の近くにあるお寺(これも名前を忘れた)の門柱の上にある小さなゾウの像。私はここをよく通るので気になって写真を撮りました。もうだいぶ前の話ですけど。
狛ゾウ 仏教の発祥はインドだからお寺に狛ゾウがあってもいいだろう。四国お遍路に行った時に第62番だったかにも門前い狛ゾウがいた。これは文京区の白山の交差点の近くにあるお寺(これも名前を忘れた)の門柱の上にある小さなゾウの像。私はここをよく通るので気になって写真を撮りました。もうだいぶ前の話ですけど。 
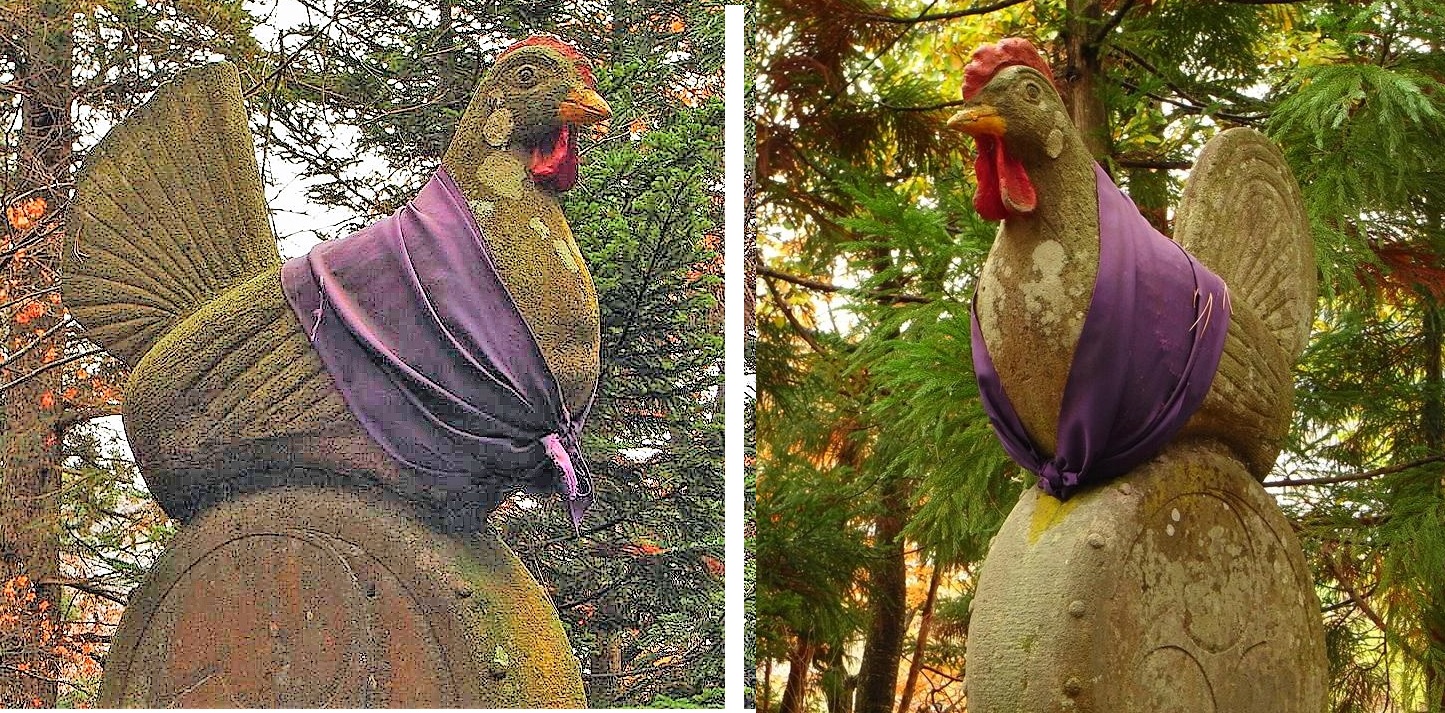 戌年=狛犬 世界一大きな狛犬、岐阜県の美濃焼の狛犬。世界一というが、狛犬のルーツといわれるのはエジプトのスフインクスなので日本一といって置く方が無難だと思う。岐阜県美濃の八王子神社。岐阜県の瑞浪にある東濃地科学センターの友人から教えてもらって昨年暮れに行ってきました。 でかい、よく作ったものだ!
戌年=狛犬 世界一大きな狛犬、岐阜県の美濃焼の狛犬。世界一というが、狛犬のルーツといわれるのはエジプトのスフインクスなので日本一といって置く方が無難だと思う。岐阜県美濃の八王子神社。岐阜県の瑞浪にある東濃地科学センターの友人から教えてもらって昨年暮れに行ってきました。 でかい、よく作ったものだ! 亥年=いのしし、京都御所の近くの護王神社はイノシシ神社で有名。さらに建仁寺の隣にある摩利支天にも同じ形のイノシシがある。一昨年歩きまわって探したものです。
亥年=いのしし、京都御所の近くの護王神社はイノシシ神社で有名。さらに建仁寺の隣にある摩利支天にも同じ形のイノシシがある。一昨年歩きまわって探したものです。 






 子の年(2020年)19年の暮れに年賀状のために京都大豊神社まで行ってきました。
子の年(2020年)19年の暮れに年賀状のために京都大豊神社まで行ってきました。 丑年(2021年用)文京区の牛天神にありました。牛は天神のお使いです。なのでガードマンである狛犬とは違うのですが、ここでは一対になって阿吽の狛犬風になっています。
丑年(2021年用)文京区の牛天神にありました。牛は天神のお使いです。なのでガードマンである狛犬とは違うのですが、ここでは一対になって阿吽の狛犬風になっています。 寅年、京都の鞍馬山は義経が修行をした寺。毘沙門天を祀っている。寅は毘沙門天の守り神。でもここでは狛犬風。ちなみに東京神楽坂の毘沙門堂にも同じような狛寅があります。
寅年、京都の鞍馬山は義経が修行をした寺。毘沙門天を祀っている。寅は毘沙門天の守り神。でもここでは狛犬風。ちなみに東京神楽坂の毘沙門堂にも同じような狛寅があります。