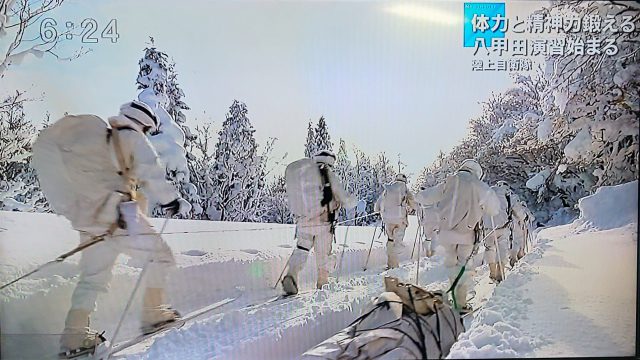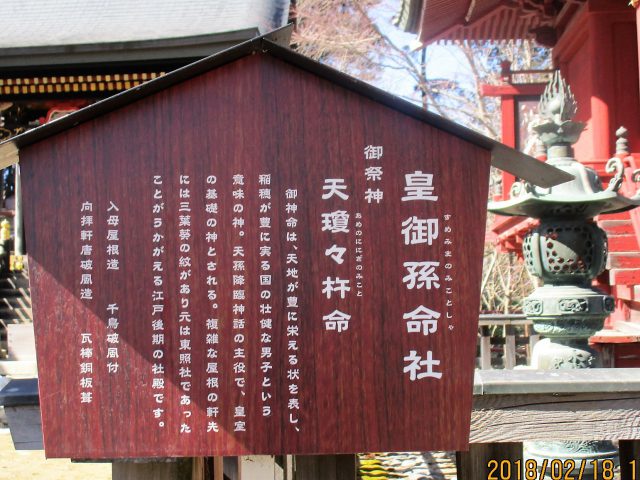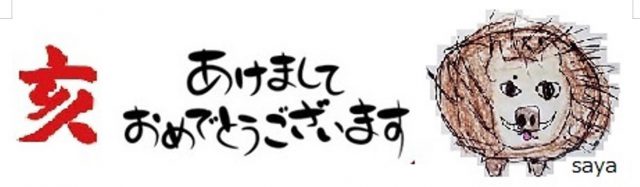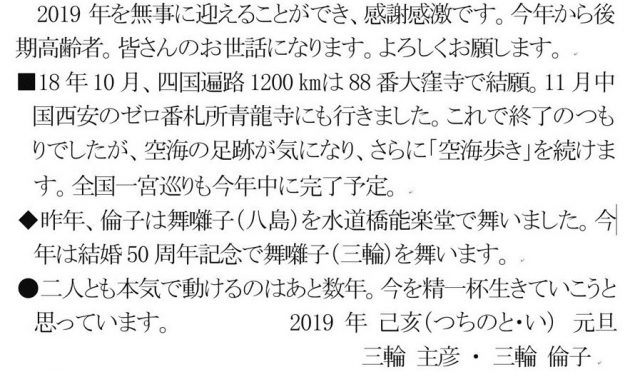越後湯沢に来ています。雪が解けて新緑が輝くこの時期が一番好きな季節です。里にはもう桜はないと思っていたら、枝垂れ桜がちょうど満開でした。なんかすごく得したような気分です。
 電動自転車で岩原の上にある超人気のイタリアンのお店に行きました。電動はすごい。リフト1本分を軽く乗り越えてしまうのだから。珍しくナントカパスタを食べ、コーヒーを飲んでゆっくりしました。
電動自転車で岩原の上にある超人気のイタリアンのお店に行きました。電動はすごい。リフト1本分を軽く乗り越えてしまうのだから。珍しくナントカパスタを食べ、コーヒーを飲んでゆっくりしました。
目の下に関越高速道路が見えます。店を出て駐車場へ。ここから遠くに神楽峰のスキー場が見えます。まだまだ雪がいっぱい。目の下には関越高速道が谷川岳に向かって伸びています 。

この写真の中の矢印が我がマンション。平成の前から我が家はスキー用ハウスとして持っていました。スキーができない時期には「おやじの隠れ家」として利用しています。大浴場とサウナ、トレーニングルームも完備しているので、ごろごろするには最適です。
来年も隠れ家にしばしば隠遁しようと思っていたところ、奥様、子どもから「終活をするように」との厳命が下った。第1弾として車の処分が終わり、第2弾として我が唯一の不動産の処分に取り掛かることにした。
4月に地元の不動産「ひまわり」に売り出しを頼んだ。
来年のスキーはここではできそうもないし桜も見られなくなる。残念なことだがもう年なので仕方がない。 ということで本日はセンチメンタルジャーニー!
ということで本日はセンチメンタルジャーニー!
だれか、引き継いでくれないかな・・・!!