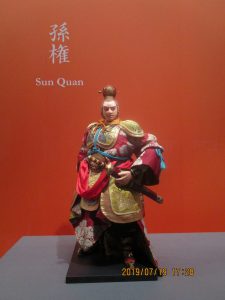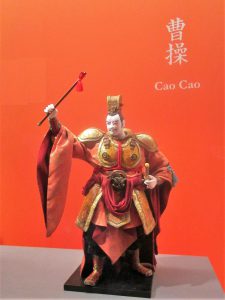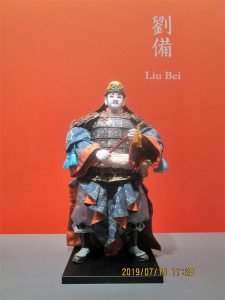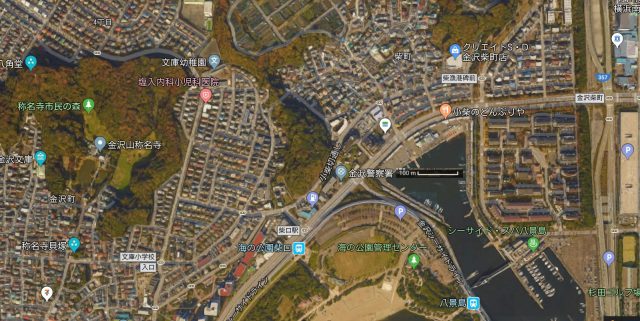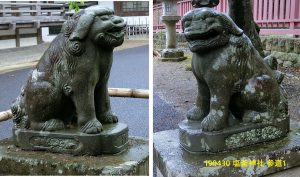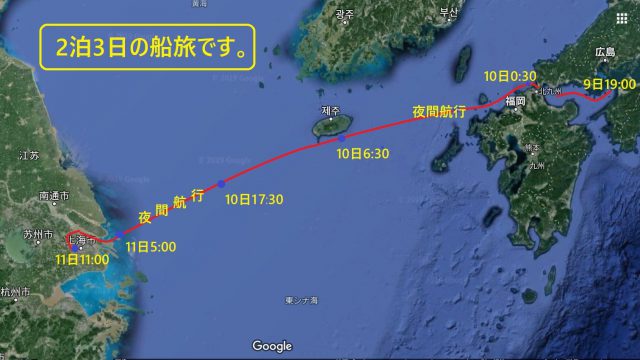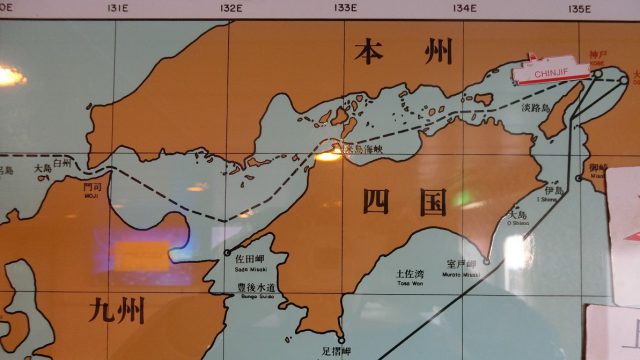大勢の方から「ブログの更新がない!生きてるか?」の連絡をいただきました。大勢と言っても2人ですが・・・実は最近フェースブックというほうにはまって、そちらでは1週間に2回ぐらい、狛犬シリーズをやっています。
今評判の悪いGAFA(ガーファ)(Google、Apple、Facebook、Amazon)のFacebook は使い方によってはブログよりも幅広く、面白いものです。本名で、顔写真を出さなければいけないので信頼性はありますが、抜け道はいくらでもあるようです。誹謗中傷はありますが、友達間だけで行き来する分には問題ありません。と言っても個人情報はさらされるので、どこまでゆだねるかは自己責任ですが。
我が奥さんは絶対やりたくないと嫌悪感をもっています。もしかするとその方が健全かもしれません。私の友人もかなり拒否反応を持っている人も多いようです。
GAFAをめぐってはアメリカと中国の覇権争いが深刻になっています。トランプ大統領は中国のHuaweiを排除してGAFAを守ろうとしましたが、もうすでにHuaweiとGAFA は深い中になっており分離するのは難しいのが現状です。アメリカや日本はHuawei 技術を盗まれると言っています。しかしHuawei製品に日本アメリカの技術部品が詰め込まれているのですから、ブーメラン現象でアメリカ日本も深刻な影響を受けるのです。
企業の方が大統領や首相よりも頭がいいので、今後はHGAFAとなって共存を目指すと思います。これら巨大企業はすでにちょっとした国レベルの経済力影響力を持っています。私たちはどうしたらいいのか?? これら企業のサービスを拒否することができればいいのだが、もうムリだろう。
そんなことは百も承知の安倍政権は消費増税を期にマイナンバーカードを導入して一気にIT国家(GAFA優先の)になろうとしている。しかしIT大国の中国、韓国、アメリカの現状をみたほうがいい。ちょっと立ち止まっているとIT後進国になる。しかしその方が一般国民は幸せだと思う。
マイナンバーカードにすべての情報(預金口座、大学入試センターの成績、カード履歴、旅行履歴、など)を入れてビッグデータを作り、それで経済をコントロールするつもりだ。政権側にとってはこんな便利な方法はない。国民もこんな便利になって幸せ(上海での見聞)という。日常は便利で楽しいが情報はすべて国家(企業)管理(FacebookやGoogleは使えない)になっており好きなことも言えない。
我が家はマイナンバーカードを申請するつもりはない。どんな政権であっても国家統制(GAFA統制)下に入りたくない。……と強がっても、なし崩しにその方向に進むのだろうなぁ。若い連中は、「そんなこと言ったって時代の流れですよ!」という。「流れ」に逆らっても流されると100年前に夏目漱石が言っている。今は「空気を読む」ということらしい。
 脚立に乗って取り付けるのがちょっと不安だったので、業者に頼んだが、断ったので自分で取り付けるしかなくなった。これぐらいは3年前までは難なくやっていたが、年寄ると脚立の上で上を向いて作業をするのは結構きつい。今は器具は進化しており取り扱いは簡単になっている。業者は26,000円と言っていたが、12,000円でできた。奥さんから手間賃8,000円をもらった。久しぶりに仕事をした感じだ。
脚立に乗って取り付けるのがちょっと不安だったので、業者に頼んだが、断ったので自分で取り付けるしかなくなった。これぐらいは3年前までは難なくやっていたが、年寄ると脚立の上で上を向いて作業をするのは結構きつい。今は器具は進化しており取り扱いは簡単になっている。業者は26,000円と言っていたが、12,000円でできた。奥さんから手間賃8,000円をもらった。久しぶりに仕事をした感じだ。