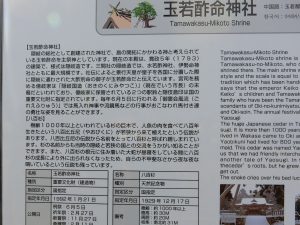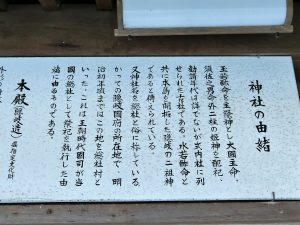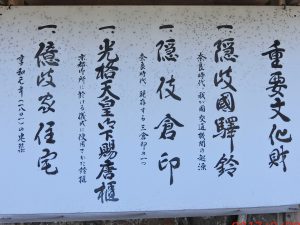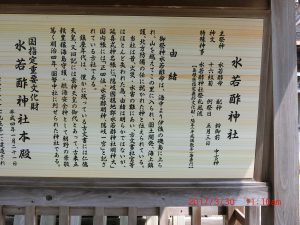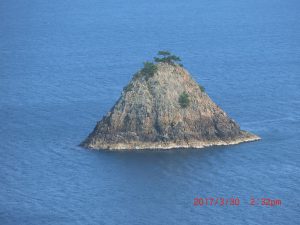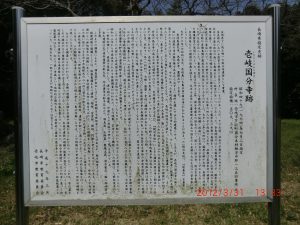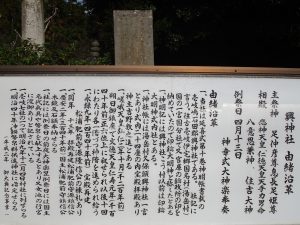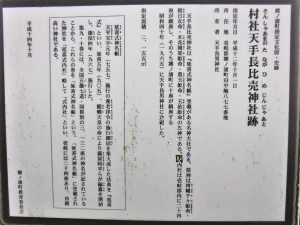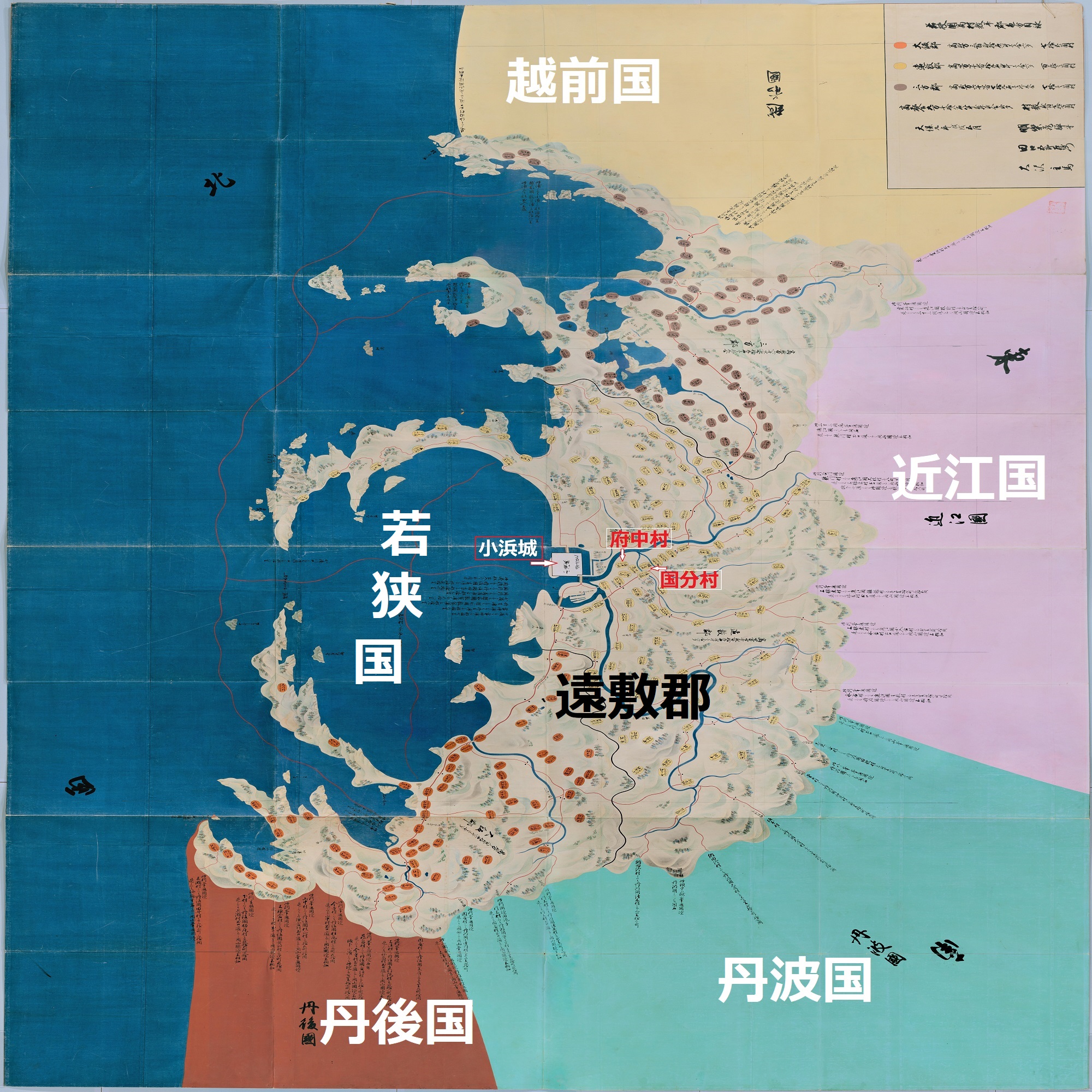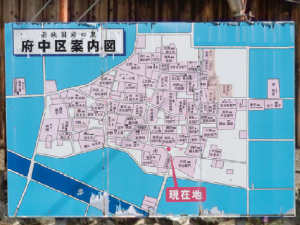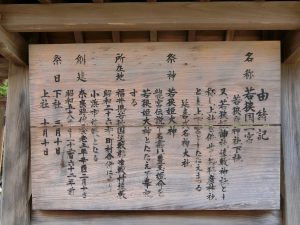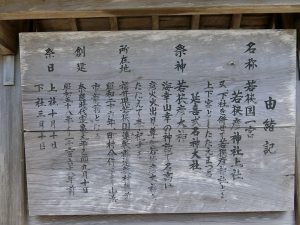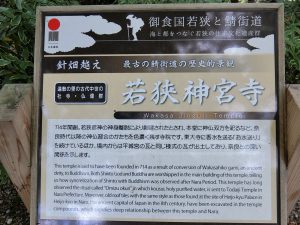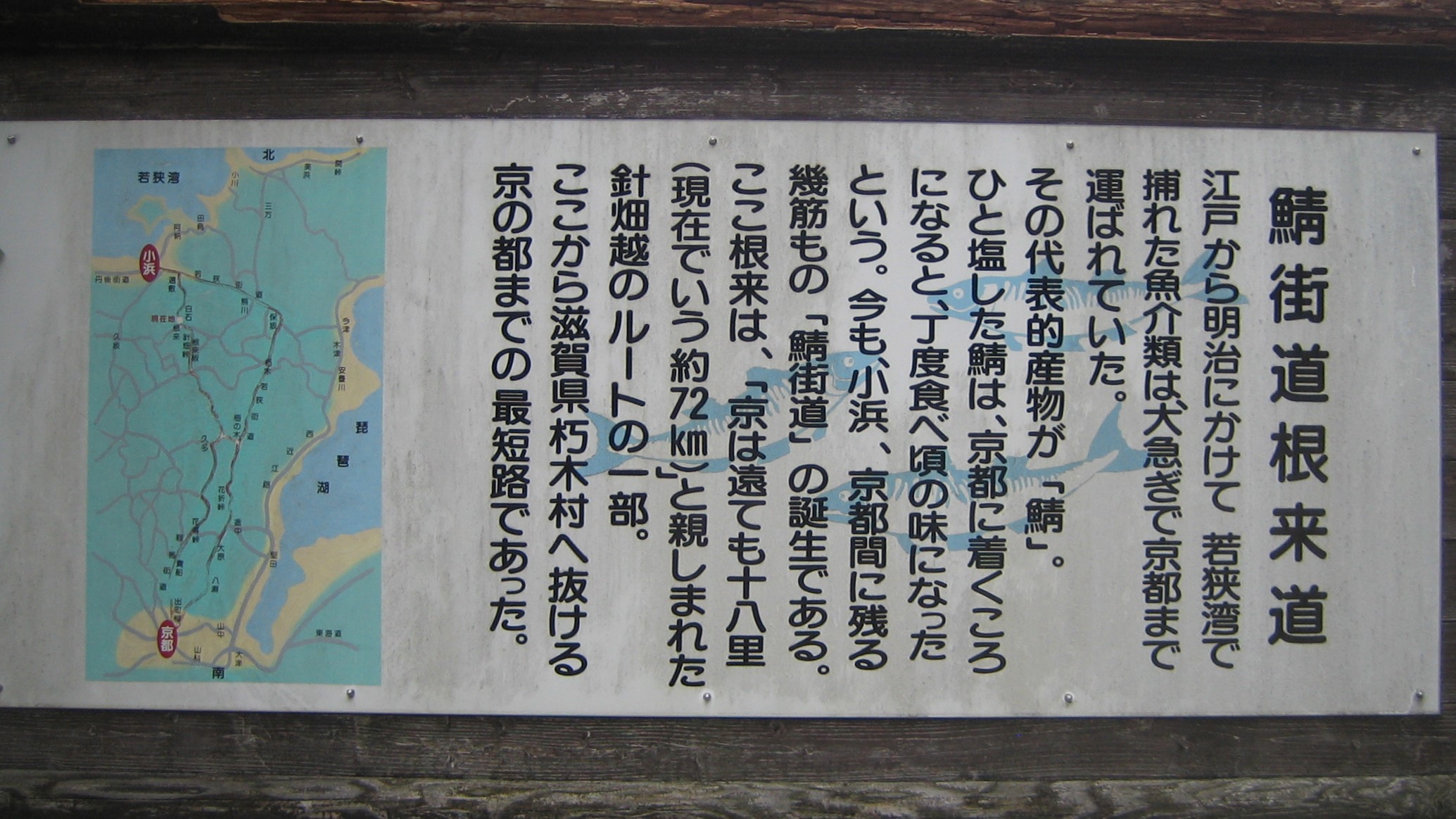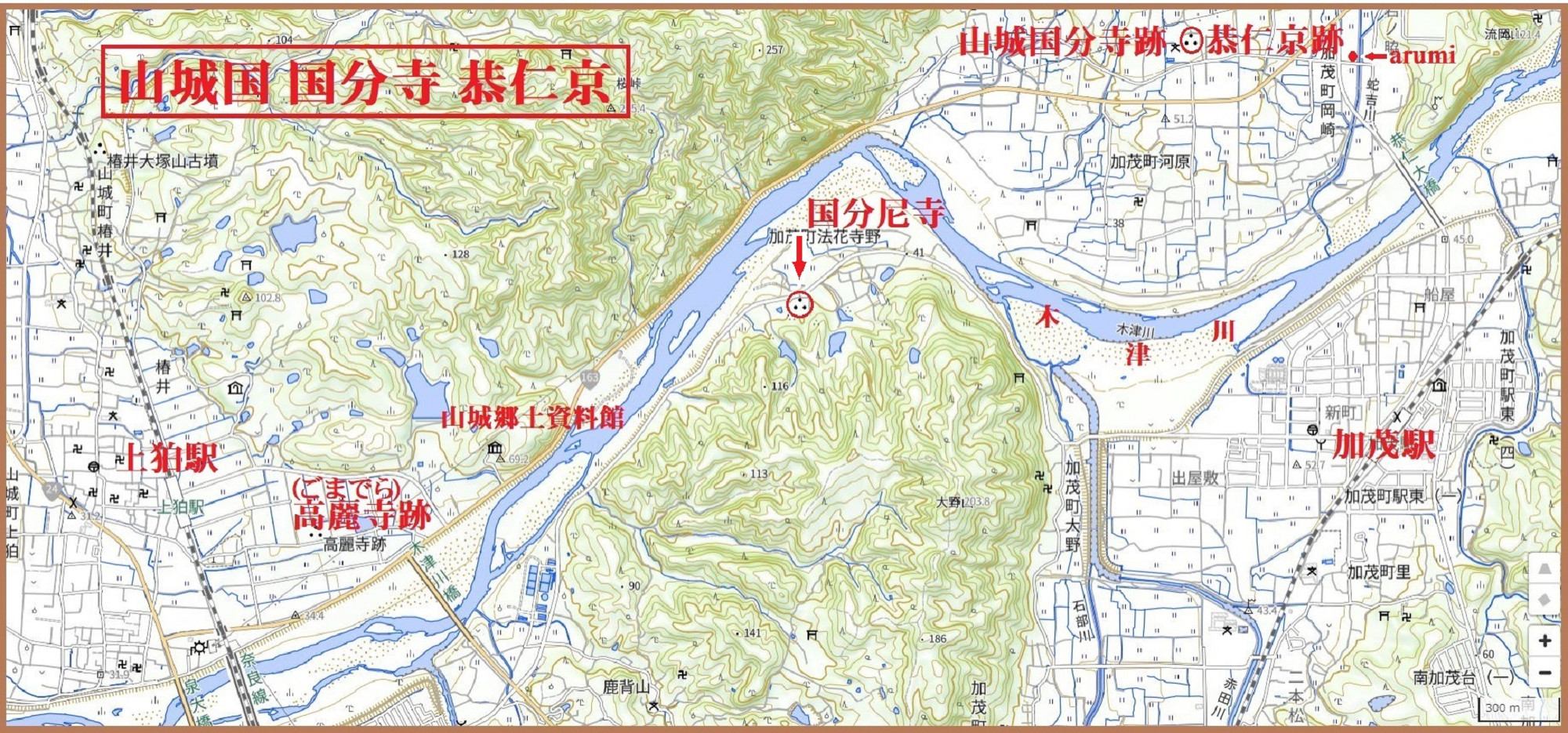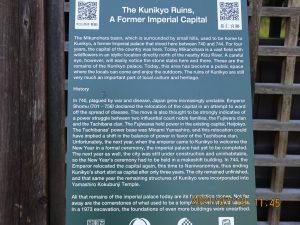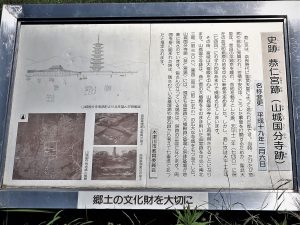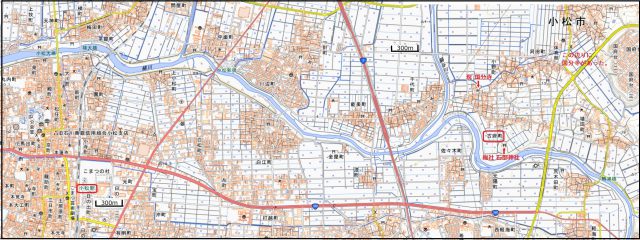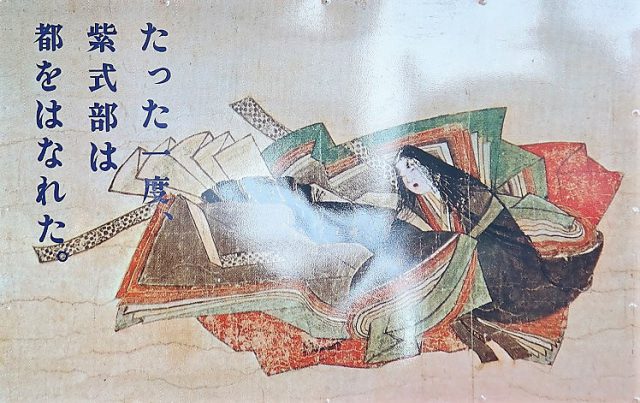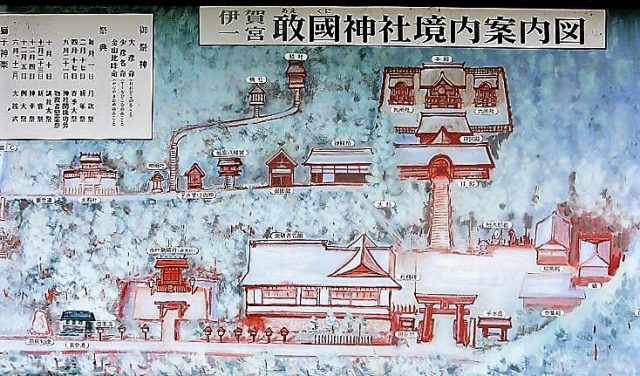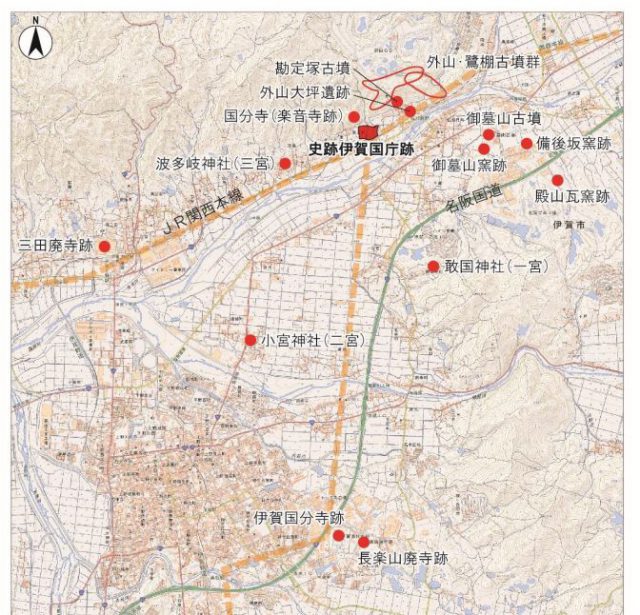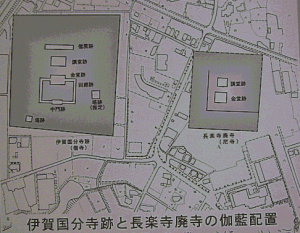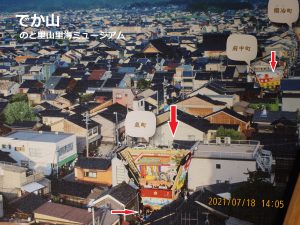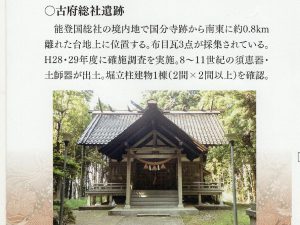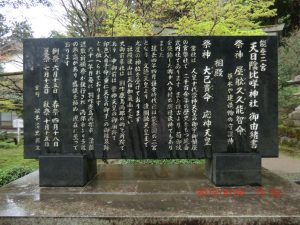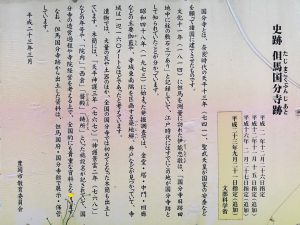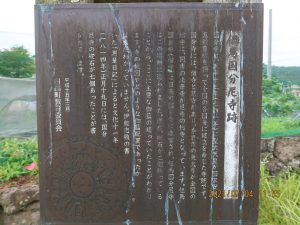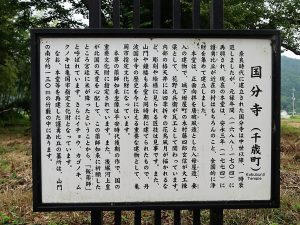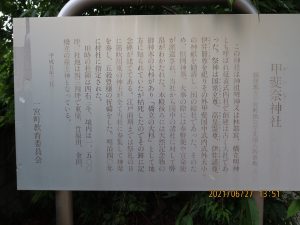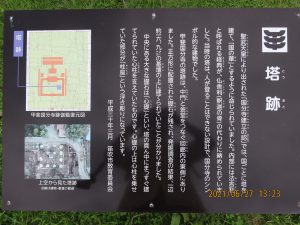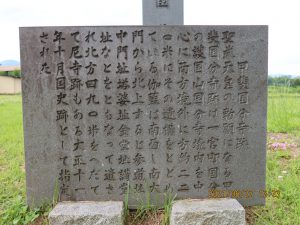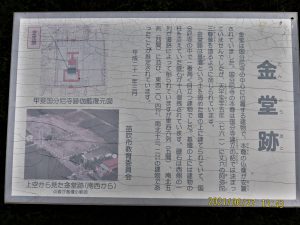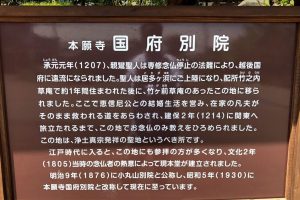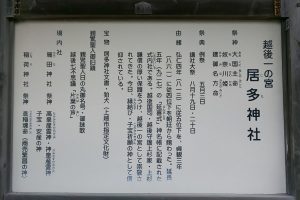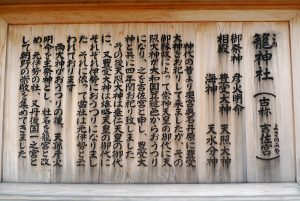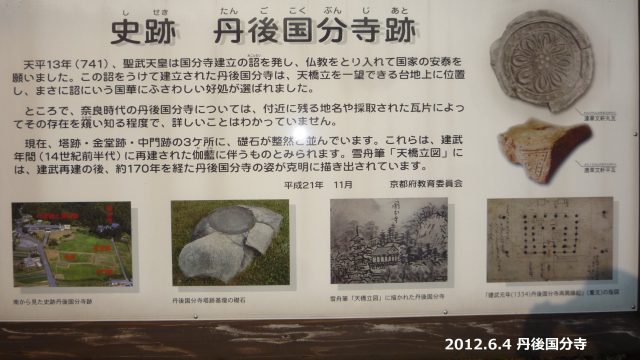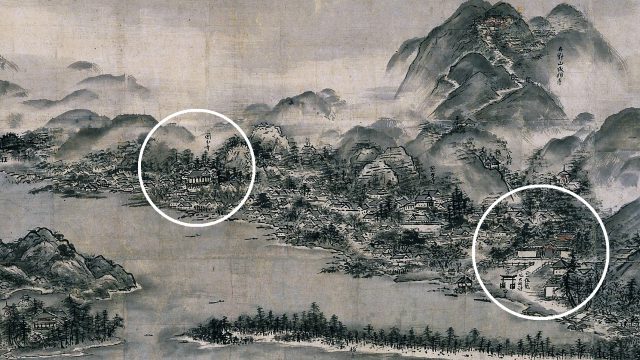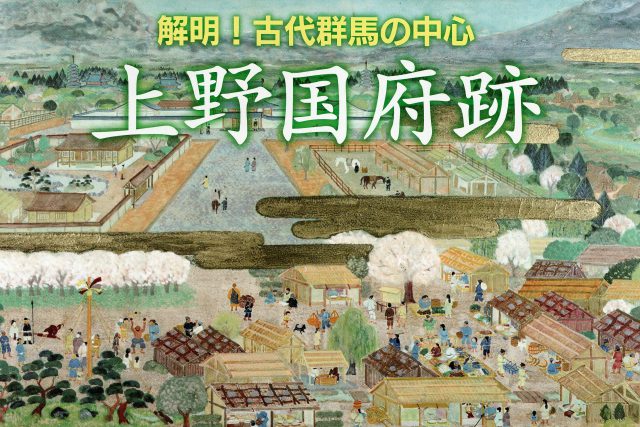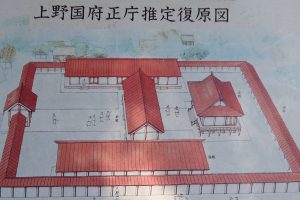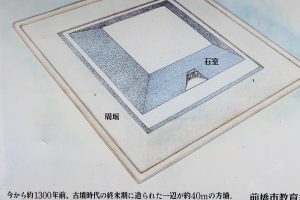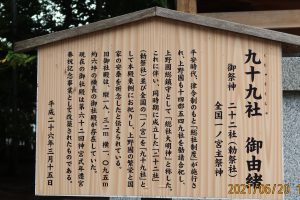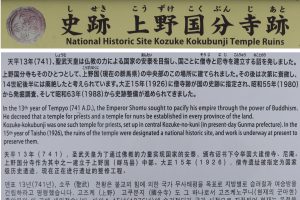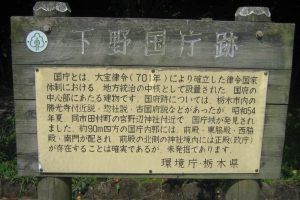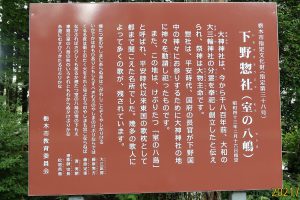島根半島の北方約50 kmに位置する島々で、隠岐群島とも呼ばれる。大きな島は本土に近い島前と空港のある島後のふたつである。島後は単独の円錐形の島だが、島前は沈水した火山でカルデラ部分に海水が侵入している。地形的には対照的な二つの島だ。国府、国分寺は島後にあるが、後醍醐天皇が流刑になった黒木御所は島前にある。
- 島前の島々 焼火山が中央火口丘
- 最高所は600mもある。周囲は断崖絶壁
国府 総社
隠岐の国を作ったのは水若酢と玉若酢の二柱の神さまである。玉若酢命を祭る玉若酢神社の地に国府があり、総社の役割をしていたという。国府の遺構はわからない。
- 山の上に甲(こう)ノ尾城=国府
- 西郷町甲(こう)野原=国府
- 億岐氏が宮司を務める
- 国府とある。
- 八百杉の巨木
- 古くから人々が住んでいた
- 出雲大社風の大しめ縄
- 隠岐造りの本殿(大社造り)
- 印璽をあづかる印鑰(やく)神社
- 玉若酢神社宮司は億岐家
国分寺
現在の国分寺が古代の国分寺を受け継いでいる。国分寺に後醍醐天皇の行在所が作られた。しかしその後行在所は島前の黒木御所に移った。古代国分寺の建物の礎石が境内に残されている。
- 現在の国分寺、古代国分寺の跡
- 2009年火災、発掘調査でわかる
- 現在国分寺の山門
- 火災後再建なった本堂
- 古代国分寺の礎石
- 後醍醐天皇の行在所
- 後醍醐天皇を祭る鎮護社
- 後醍醐天皇
国分尼寺
国分寺の隣に隠岐の常設の闘牛場がある。ちょっと驚き。国分寺から500m離れたところに国分尼寺跡がある。
- 年3回本場所、地方場所もあり
- 国分尼寺跡 ピンボケだ!
- 国分尼寺跡、今は畑
隠岐一宮 水若酢神社
島後の内陸部にある。祭神は水若酢命、本殿は隠岐造りで立派。
- 立派な隠岐造りの本殿
- 立派な土俵がある。
隠岐一宮 由良姫神社
島前にも一宮がある。イカ寄せの行事があるそうだ。
- 由良姫神社 イカ寄せ
- これも立派な本殿
島前 中央火口丘 焼火神社
島前の島々は中央の焼火山を囲むように取り巻いている。登ってみたらすばらしい神社があった。
- 島前の真ん中に焼火(たくひ)山がある。
- 焼火山神社、山上にある。
- 岩に食い込んでいる社殿
- 宮司さん宅が山腹にある。
隠岐諸島は火山の島、断崖絶壁 おまけ